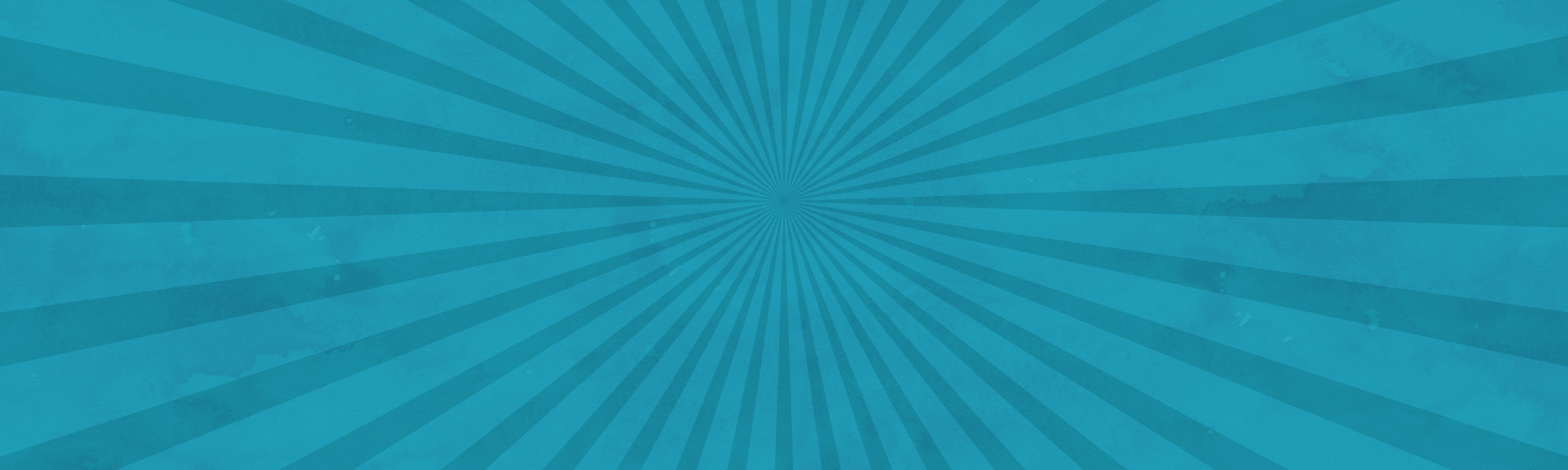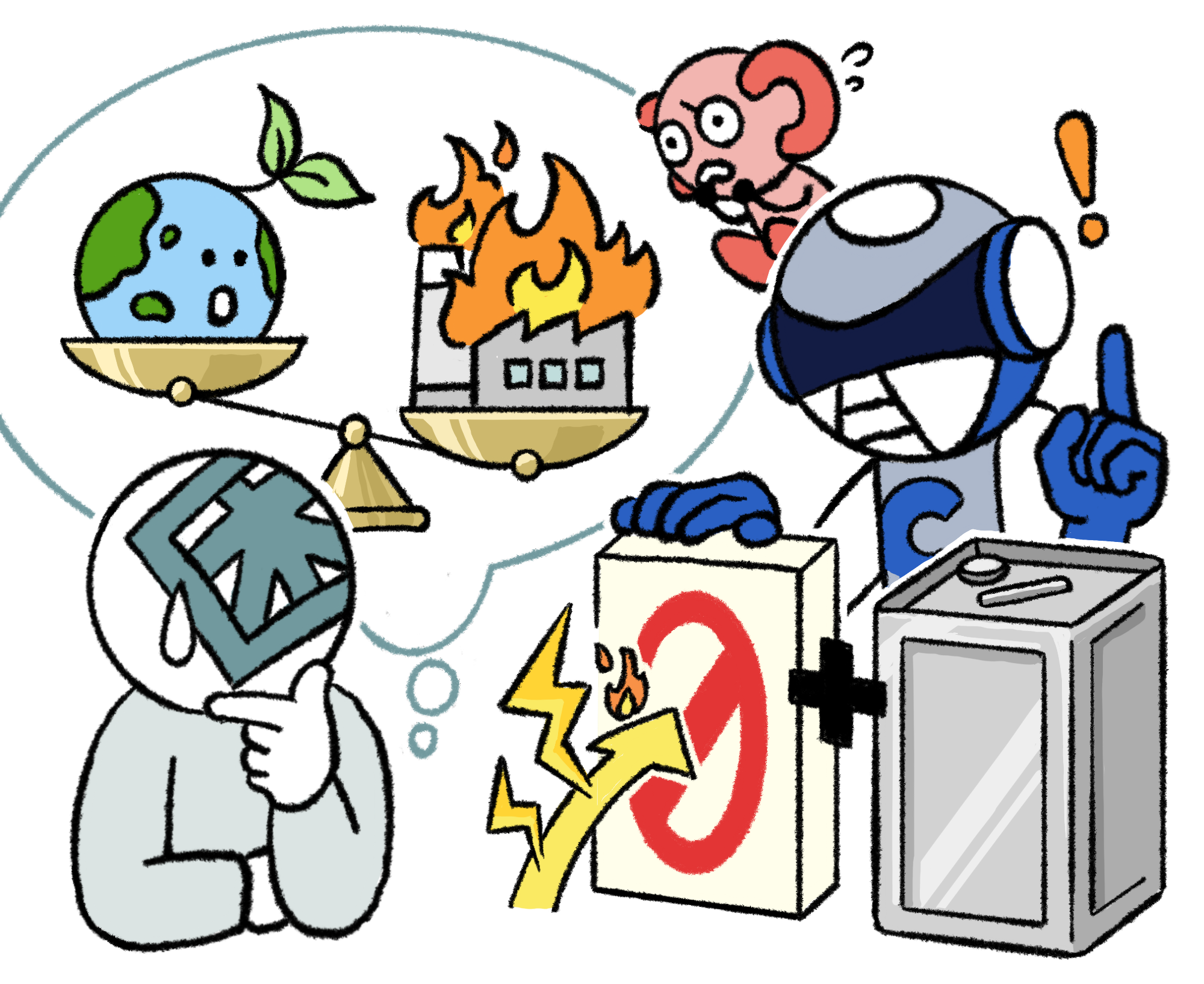
近年、環境配慮などを含むSDGs目標への貢献や働きにより、材料や薬品などの切り替えがものづくり企業で進んでいます。
それは製品の洗浄工程に使用する“洗浄剤”も同様です。
その中でも炭化水素系洗浄剤への切り替えが増加していますが、引火性のある洗浄剤であるため、安全面を懸念する企業も少なくありません。
ご相談者さんも、その安全性でお困りのようです。

炭化水素系の洗浄剤は金属への腐食性が少なかったり、比較的安価だったりと魅力的な部分が多く切り替えの検討をしているのですが、引火性があり消防法に該当するため、火災などの恐れから安全面に不安があります・・・。

ご認識の通りです!
メリットの多い炭化水素系の洗浄剤は、近年SDGs目標への貢献の観点から注目されている洗浄剤のひとつです。御社のように安全面の懸念から導入に踏み込めていない企業もありますが、その認識は間違いです。

(ラボボス)
炭化水素系の洗浄剤は引火し危険だと思っている人が多いが、実は洗浄液単体では火災を起こすことはなく、3つの要素が揃わない限り問題ないのじゃ!

3つの要素が原因なんですね!
それらを知ることができれば、炭化水素系の洗浄剤を導入しても問題なさそうです!
炭化水素系洗浄剤の安全性
ものづくり現場の洗浄工程では、これまで様々な洗浄剤が使用されてきました。
不燃性溶剤のフロン・エタンはオゾン層破壊問題により製造中止となり、油分の溶解力が高い塩素系洗浄剤のトリクロロエチレンやジクロロメタン、臭素系洗浄剤の1-ブロモプロパンが使用されてきましたが、発がん性や生殖毒性といった観点から、炭化水素系洗浄剤へ切り替える企業が増えています。
炭化水素系洗浄剤は、金属に対する腐食性が低く、加工油などの脱脂洗浄に優れた性能を発揮します。
加えて、蒸留再生によって繰り返し使用できるため、環境に優しい洗浄剤と言えます。
しかしながら、引火性液体であるため消防法に該当し、洗浄機を使用する際には安全面への対策が重要となります。

炭化水素系洗浄剤は、金属への腐食性が少なく加工油の脱脂洗浄に優れているうえ、蒸留再生しながら使用できます。
炭化水素系洗浄剤で火災が起こる理由
炭化水素系洗浄剤は引火性があるため、「火災」のリスクが気になるところですが、燃焼が起きるには燃焼の3要素がすべて揃う必要があります。
燃焼が起きるための3要素とは、
- 可燃物・可燃性の液体
- 空気 (酸素)
- 着火源
これら3要素が揃って初めて燃焼が起こります。
つまり、炭化水素系洗浄剤を安全に使う鍵は、この「燃焼の3要素」を「揃わせない」ことにあります。
炭化水素系洗浄剤を安全に使用するためには?
炭化水素系洗浄剤は引火性液体であるため、燃焼の3要素から「可燃性液体」の要素を取り除くことはできません。
そこで、炭化水素系洗浄剤を使用し安全に運用するには、燃焼の3要素を揃えないよう着火源もしくは空気を遮断する必要があります。
では、どのように着火源や空気を遮断するのでしょうか?
火元を遮断する
火元とは、火、熱、静電気などが挙げられ、現場や工程の状況により遮断方法は異なります。
- 電気回路のショートなどの火花: 電気回路を専用のBOX内に収容し炭化水素のガスが入ってこないよう、エアーを充満させて陽圧にするエアパージをしながら運用します。
- 静電気: 循環ろ過などする場合は、配管にアースを設けることが重要です。
- 加熱: 洗浄剤を加温して使用する場合、電気ヒーターなどの直接加熱は避け熱媒体油や蒸気などを用いた間接加熱を採用します。
- その他: 周囲に直火や高温部がある場所での使用は避けてください。

直火を使う工程の近くで使用してはいけません。
空気を遮断する
炭化水素系洗浄剤を使用しベーパー(蒸気)洗浄や蒸留再生する場合、炭化水素系洗浄剤を高温に加熱するためベーパー洗浄時は洗浄槽を、蒸留再生時は蒸留釜内を減圧し空気を遮断することで安全性を担保します。
製品を完全乾燥させる
炭化水素系洗浄剤は、一般的に沸点が170℃以上のため常温では乾燥できません。
そのため、乾燥には熱風乾燥や真空ベーパー乾燥などの手法が用いられますが、ここで特に注意が必要なのは、乾燥が不十分なまま製品を取り出すことです。
高温になった製品に洗浄剤が残っていると、それが蒸発し、大気中に拡散します。
この際、着火源があると火災を引き起こす危険性がありますので、必ず製品が完全に乾燥した後に製品を取り出しましょう。

必ず完全乾燥した後に製品を取り出しましょう。
完全乾燥せず火災になってしまう場合の要素
炭化水素系洗浄剤が被洗浄物に付着したまま取り出すと、火災を引き起こす恐れがあります。
では、どんな場合に乾燥が不十分となってしまうのでしょうか?
設計容量(重量)オーバー
洗浄機を設置する際、製品を完全に乾燥させるための条件を設定しますが、その設定した容量(重量)を上回る製品を投入すると乾燥不良が起こりやすくなります。
洗浄機側の乾燥時間の変更等で完全に製品が乾燥するよう調整しましょう。
樹脂製治具の使用
製品のキズ防止などの目的で樹脂製の治具を使用するケースがありますが、静電気が発生しやすくなったり樹脂は蓄熱されにくいことから乾燥不良が起こったりします。
乾燥時間の見直しや導電性樹脂の使用などもご検討ください。
このように、炭化水素系洗浄剤は優れた洗浄力と環境性能を持つ一方で、引火性に対する正しい理解と適切な安全対策が不可欠です。
安全な洗浄プロセスは、生産性向上にも繋がる重要な要素です。
炭化水素系洗浄剤の導入をご検討中、あるいは現在の運用について安全面でご不安がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。

なるほど!可燃物・空気・着火源がそろってしまうと火災の発生につながるんですね!
また、洗浄機の容量や導電性樹脂を使用した洗浄治具の使用など、日常的に意識すれば安全に使用できそうで安心しました!

洗浄品質やコストだけでなく、作業員が安全に洗浄剤を使用し作業できることも現場作りを進めていく中で大事な観点となります。

そうですよね!
炭化水素系洗浄で洗浄した後の乾燥工程で乾燥不良があると、火災を引き起こす恐れがあるとのことですが、十分に乾燥できる方法はありますか?
あったら詳しく教えてほしいです!

もちろんです!
必殺技でご紹介します!

ご相談・お問い合わせはこちらなのだ!