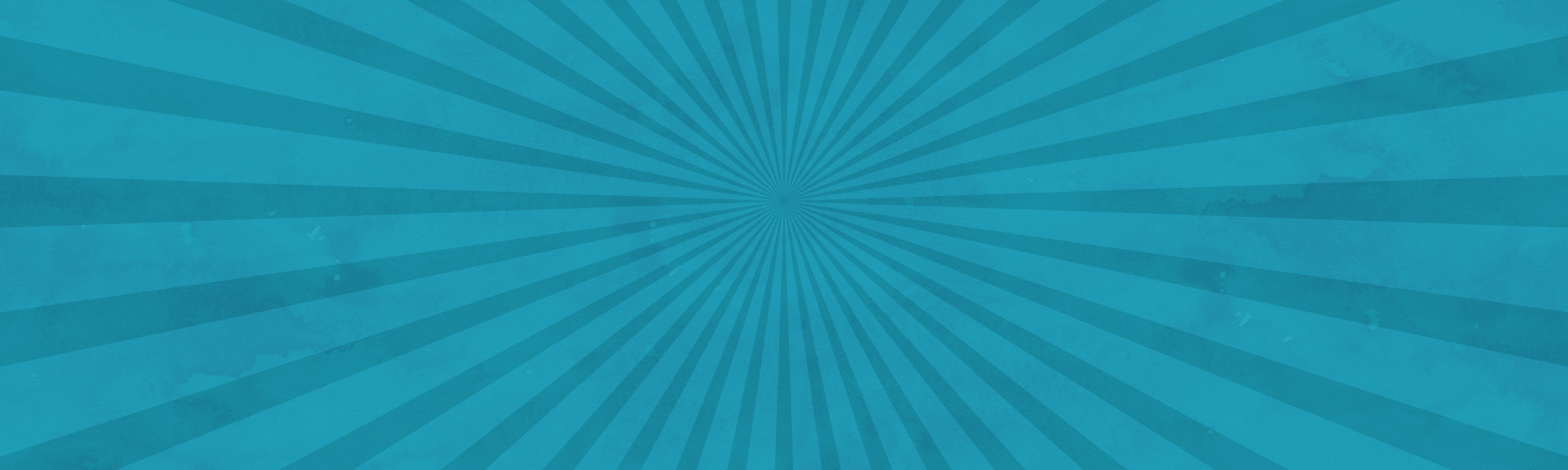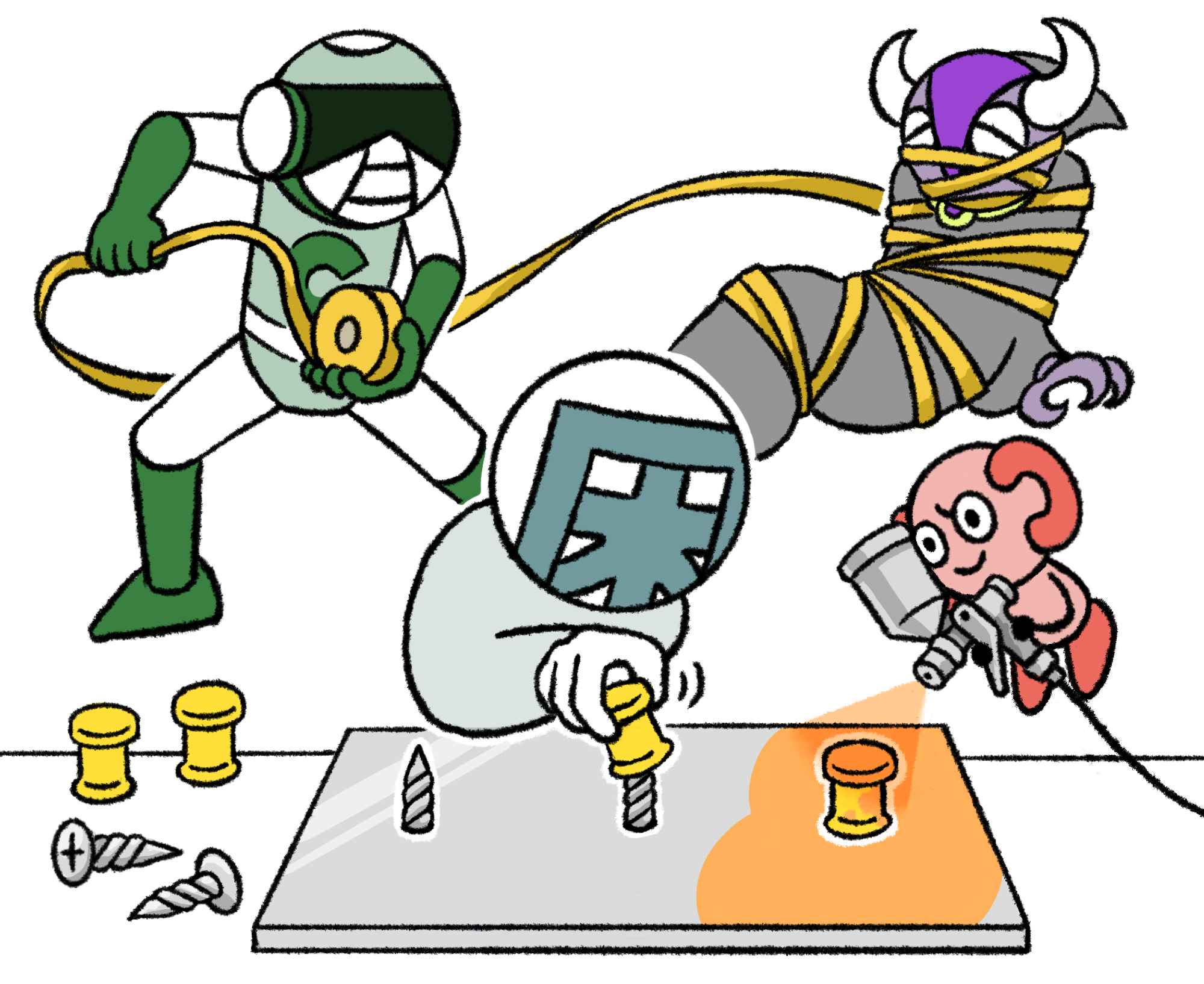
塗装部門に所属するお悩みさんは、会社から指摘されている業務の「効率化」について、どの工程で実現できるのか考えているようです。
各工程を振り返ってみると、マスキング作業に時間がかかっていることに気づきました。
この点を改善すれば、作業全体の効率化につながるかも・・・一体どんな状況なのでしょうか?
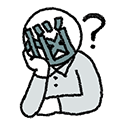
ねじ部分に塗料が付着しないよう塗装前にひとつひとつマスキングテープで保護してるのですが、意外と手間がかかり大変です。
今より効率的に進める方法はないのでしょうか?

ムーダー
おやおや、マスキングについてお悩みのようですね。
テープ以上にねじ部分を確実にマスキングできるものはないので、今まで通りの作業が1番ですよ~ヒヒッ
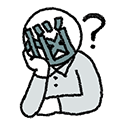
う~ん、でも会社からは業務の効率化を求められているし、細かい作業で大変なんですよね・・・

ムーダー
いやいや!テープに勝るものはありません!貼るだけなので手軽ですし!
(テープを使い続ければ廃棄するゴミは増え続けるし、コストも手間もかかるぞ~ヒヒッ)

ちょっと待ったぁ!!
ネジ部分はテープ以外でもマスキングする方法があります!
そのうえ、なんとテープを貼るより格段に短い作業時間で済むんですよー!

えぇ!本当ですか!?
作業時間が短縮できて手間がかからないなんて、まさに理想通りのマスキング方法ですね!
でもそんな簡単にできるマスキングで不良が出たら元も子もないのですが、大丈夫でしょうか?

問題ありません!
簡単かつ確実に塗料の付着を防ぐマスキングの世界をご紹介します!

ムーダー
くぅ~~~なんでいつも勝てないんだ・・・
次こそ必ず・・・!
塗料を付着させないために
塗装する際、ワークによっては塗りたい箇所と塗りたくない箇所が生まれる場合があります。
それはデザイン上の理由や、アースを取るなど機能的な目的から塗り分けが必要となるのです。
そのような塗りたくない箇所に塗料が付着しないよう保護するのが、「マスキング」や「養生」と言われるものです。
マスキングの種類
マスキングにも種類があり、使用する場面や求めるものによって選択する種類が異なります。
今回は代表的な5種類のマスキングについてご紹介します。
①テープ
マスキング方法として最もスタンダードな方法で、素材の形状に沿って保護ができます。
テープでのマスキングは直線的な箇所に対し最適ですが、マスキング箇所が曲線であったり独特な形状をしていたりする場合、テープをカットしする必要があります。手間がかかり、量産が必要な場合は生産性に大きく影響する恐れもあります。
メーカーごと様々なラインナップがあり、どれを使用すればいいか選ぶのは難しいですよね。
そこで下記2つのポイントからどのテープがよいか選びましょう。

マスキングテープ
- テープの耐熱温度
使用する塗料の焼き付けによってテープ素材が溶けたり焦げたりする恐れがあるので、耐熱性を確認しましょう。一般的に耐熱性は以下のような順で高くなっていきます。和紙 < クレープ < ポリエステル < ポリイミド
テープ素材だけでなく、粘着層の耐熱性も忘れてはならないポイントであり、粘着層の耐熱性が低いと焼き付けた際に粘着層が貼りついてしまい、テープがきれいに剝がれなくなってしまいます。一般的には以下のような順で耐熱性が高くなるので、参考にしてください。
ゴム < アクリル < シリコン
- テープの接着強度
マスキングする素材の表面状況や種類により、粘着性の低下、塗装時の剥がれ、塗装後の剥がしにくさといった問題が生じます。接着強度が選べるものもありますので、使い方に合わせて適切なものを選定しましょう。
②シール
丸い形から四角い形、位置決めがしやすいよう模様がついたものまでシールと一言で表しても、その種類は豊富です。
また既製品だけでなく、テープの原反(細くカットしていない状態)を剥離紙などに貼りつけ、製品にあわせた型やプロッターでカットして製品にあったシールを自社で製造し使用する方法もあります。抜き型の作成や使用しない余り部分が生まれるためコストがかかりますが、作業メリットが出るようであれば十分に時短効果が出る方法です。
また、テープやシールは製品の表面に密着しないと塗料が隙間から浸透し塗り分けすることができなくなりますので、上から密着させることが大切です。
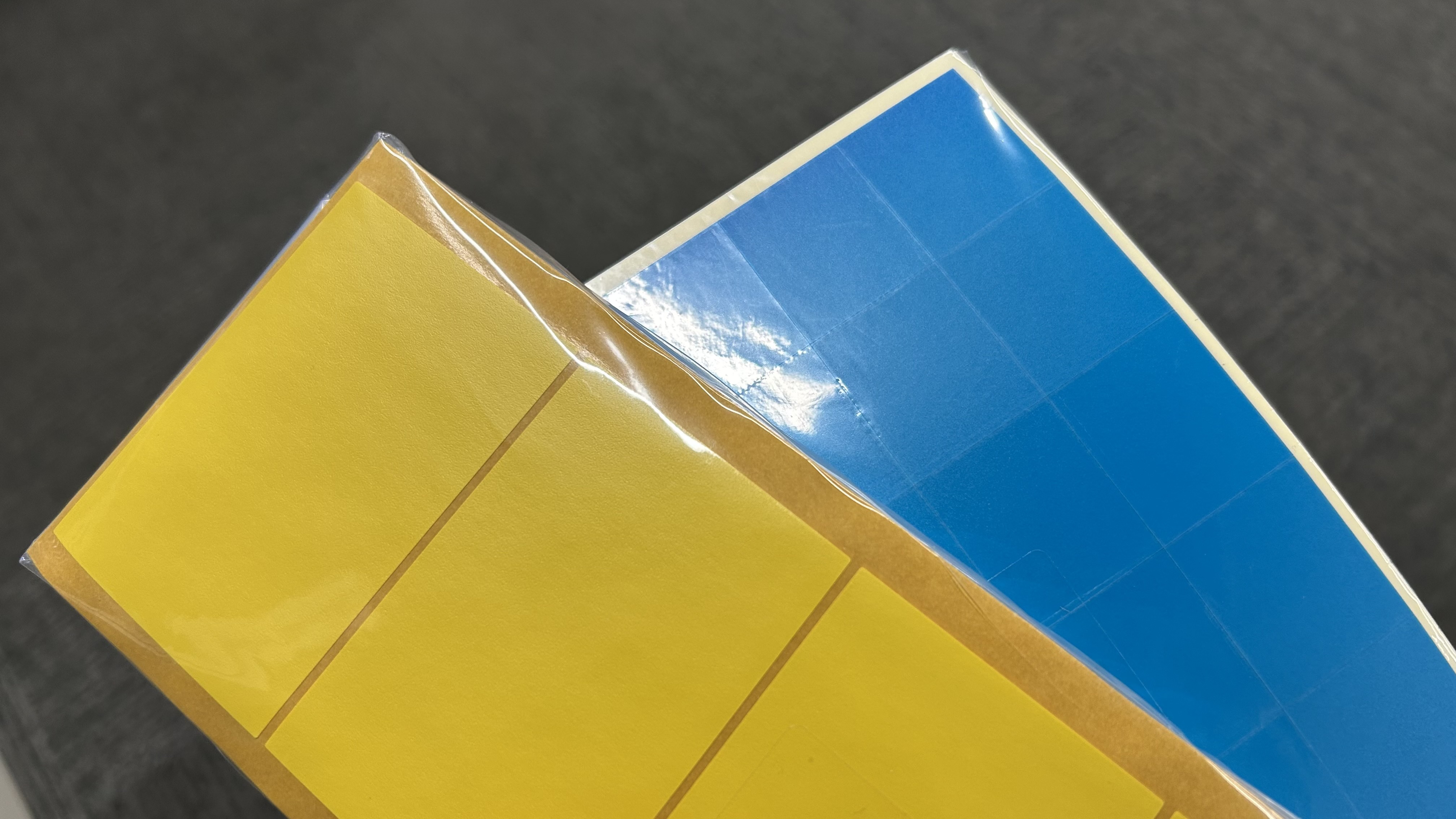
シール
③シリコン製マスキング
ねじ部や貫通穴などのマスキングにはシリコーンゴム等で作成したマスキング治具が最適です。ねじ部にねじを実際にいれてマスキングする方法もありますが、シリコーンゴム製のマスキング治具は押し込むだけでよいので手軽であるといえます。
シリコン製のため熱に強く、焼付が必要な場合に重宝されています。
様々なタイプがあり、たとえば袋穴の内部空気が抜けるような構造やねじ周りの部分もマスキングできるものなど、製品に合わせたものを選ぶことができます。

シリコン製マスキング
④樹脂・薄板製マスキング
樹脂や薄板などを素材とするマスキング治具で、製品のCADデータなどから形状を決め製作されます。専用設計となるためぴったりとはまるマスキングができます。
一般的には比較的高価なマスキング治具ですが、ある程度の数量を製作すればコストを抑えることができます。
⑤電鋳マスキング治具
製品を量産しなければならない場合、テープやシールでマスキングしていたのでは時間がかかるうえ、剥がしたゴミが厄介ですよね。
量産性に重点をおいて考えたとき、電鋳マスキング治具はワークの固定とマスキングを同時に行うことができるのでおすすめです。
プラスチックなどの製品の上にメッキを重ねて厚くしていくことで出来上がるこの治具は、製作に手間とコストがかかり非常に高価ですが、生産性の向上が期待できます。
ほかにも、マスキング箇所に塗料が多少付着しても問題ない場合は、塗りたくない面同士を合わせて治具に取り付け塗料が入り込まないようにする方法もあります。
求めるマスキングレベルや製品の形状によって適したマスキングの種類は異なりますので、選定が難しい場合は近くの専門家またはNCCまでご相談ください。
マスキングの後処理について
ここまで代表的なマスキングを紹介してきましたが、素材や塗装方法、処理数などをもとに最適なマスキング方法は見つかったでしょうか?
マスキングは塗料を付着させないよう保護することが目的ですので、どうしても”マスキングすること”に意識が持っていかれますが、マスキング後の後処理も重要です。
- テープを剥がすタイミング
テープやシールは、塗装が完全に硬化した後剥がすと完成した塗膜が割れて見切り部分がギザギザになったり、うまく剥がせないといった恐れがあります。そこで、マスキング治具は多少硬化が進んだ完全硬化する前の状態で剥がすことできれいな塗り分けが完成します。
- 定期メンテナンス
マスキング治具や電鋳治具などは繰り返し使用するため、定期的に洗浄や剥離をしなければなりません。浸漬洗浄、超音波洗浄、手で落とすなど様々な洗浄・剥離方法があり、マスキングの素材に合わせた方法を選択しましょう。塗装頻度や塗装量によってメンテナンスタイミングは異なりますが、静電塗装の電気が通電しなくなったり、塗装片の脱落によって塗装品質に影響が出たりする前に行いましょう。
マスキングは簡単な作業に見えますが、実は生産性に直結します。可能な限り手間をかけずに作業ができれば、初期費用がかかってもトータルコストが下がる可能性もありますので、様々なマスキングを使い分け自社に最適な方法を検討しましょう。
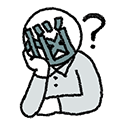
わざわざテープを貼らなくても、弊社の製品だったらシリコンプラグでマスキングすることができるんですんね!
業務効率化にも貢献できそうで、すぐに社内で情報共有したいと思います。
そこで、塗装グリーンが特におすすめのマスキングはありますか?

もちろんあります!
驚くほど充実したラインナップがある、おすすめのマスキングを必殺技でご紹介します!

ご相談・お問い合わせはこちらなのだ!